疾患・特集
体臭
体臭に関する記事をご紹介します。体臭の正しい知識を身につけることで、予防や改善にお役立てください。

仕事や学業に集中できないなど、日常生活に支障が出るほどの多量のワキの汗は、単なる汗かき体質ではなく、「腋窩多汗症」という病気かもしれません。その診断基準とは? 目次 多量のワキの汗、ひょっとして病気!? あなたのワキの汗、病気の基準に当てはまるかをチェック! 重度の場合はボツリヌス療法が行われることも 多量のワキの汗、ひょっとして病気!? 夏場にワキが汗でじっとりとして、洋服にシミができて困ったということは、多くの人が経験しているはず。しかし、市販のワキの汗を吸収するパッドなどを貼っても対処しきれないほどであれば、「腋窩多汗症」(えきかたかんしょう)という病気が疑われます。 腋窩とはワキのくぼみのことで、そこに多量の汗をかくことで人前に出られない、仕事や学業に集中できない、一日に何度も着替える必要があるなど、日常生活に支障が出ていれば、やはり単なる汗かき体質とは言えないでしょう。 あなたのワキの汗、病気の基準に当てはまるかをチェック! 腋窩多汗症は、原因によって2つに分類されます。ほかの病気や使用している薬によって引き起こされる場合は続発性(ぞくはつせい)腋窩多汗症、原因不明の場合は原発性(げんぱつせい)腋窩多汗症と呼ばれます。原発性腋窩多汗症は、以下の基準により診断されます。 原発性腋窩多汗症の診断基準 原因不明の過剰なワキの汗が6ヵ月以上続き、かつ次のうち2つ以上が当てはまる場合、原発性腋窩多汗症と診断されます。 左右のワキで、同じぐらい多くの汗をかく ワキの汗が多いことにより、日常生活に支障をきたしている 週に1回以上、ワキに多くの汗をかくことがある ワキの汗が多い状態は、25歳より前から始まった 家族や親戚の中に、同じようにワキの汗が多い人がいる 眠っているときは、ワキの汗は多くない 重度の場合はボツリヌス療法が行われることも 続発性腋窩多汗症を治療するには、まず原因を突き止め、それに対処することになります。 原発性腋窩多汗症の治療には、塗り薬や飲み薬が用いられます。重度の場合は、ボツリヌス療法が行われることもあります。これは、ボツリヌス菌がつくるたんぱく質を用いた薬をワキに注射する治療法で、神経から汗腺への信号を遮断することで、汗の量を減らすことができます。この治療法を行っている医療施設は限られているため、事前に確認しておくとよいでしょう。 なお、汗の量を抑える治療を受けても、ワキガなどの臭いを直接抑えられるわけではありません。汗の臭いが気になる場合、それが腋窩多汗症なのか、ワキガなのかを自分で判断するのは難しいので、医師に相談してみましょう。 公開日:2013/07/22

蒸し暑い季節。気になるのが汗のニオイだ。しかし実をいえば、汗腺がうまくはたらいていれば、汗がニオうことはない。問題になるのは、汗腺のはたらきが鈍ることで出る、重炭酸イオンを含む汗だ。ニオう汗を抑えて、心地よく夏を過ごすための方法を一挙ご紹介しよう! よい汗をかくための3原則 その1 冷暖房に頼るな 脳も足も使わなければ、はたらきが衰える。汗腺も同じだ。冷暖房の効いた部屋で過ごしていると、汗をかきにくくなり、それだけ汗腺機能が低下してしまう。熱い季節もなるべく窓を開け、自然の風で涼むようにしたいもの。冷房を使う場合は外気との差を5℃以内に設定しよう。 その2 体を動かそう 習慣的に体を動かすことも大切。おすすめはウォーキングやジョギング、サイクリングなどの、あまりハードではない有酸素運動だ。なお、運動の前後にはしっかり水分補給を心がけ、熱中症などにはくれぐれもご注意を。 その3 入浴でよい汗を 一風呂浴びていい汗を流せば、新陳代謝が促され、汗腺機能も鍛えられること間違いなし。ただし、湯船に入っているとき汗は蒸発しない。どっと汗が流れるのは、むしろお風呂上りなのだ。入浴後、すぐ服を着て涼むのではなく、しばらく裸のままで汗をかくようにするとベター。ただし、風邪をひかないよう冷えには気をつけて! 意外なモノを使って汗かき上手に! レモン 汗のニオイに効き目バッチリなのが「レモン」。お湯にレモン汁やレモンの精油をたらし、体を拭くと効果がある。とくに汗をかいたときは、ミョウバンを大さじ 5~6杯加えるとなおよい。ただしこの場合、必要以上に汗を拭き取らないよう、わきの下などにだけ使うようにしよう。 お酢 血行が阻害されたり、食事のバランスが崩れたりしていると、アンモニア臭で汗がニオうようになる。こんなときは、入浴直前、湯船にお酢を少々入れるとよい。おすすめは、醸造酢か黒酢。めやすは、醸造酢ならお猪口に 2~3杯、黒酢なら1杯。クエン酸が汗腺から吸収されて、アンモニアの乳酸生成を抑制。いやなニオイを抑えることができる。皮膚の雑菌繁殖も抑制でき、一石二鳥だ。湯船から出たら軽くシャワーを浴びると、お酢のニオイは消えてしまう。 炭 寝ているときの汗はねばついたニオイの強いもの。翌朝のさわやかな寝覚めのためにも、寝汗はできるだけ抑えたい。できれば、ベッドや寝室の隅に炭を置くと、マイナスイオンが出て汗の水分子が細かくなる。蒸発しやすくなるので、その分ニオわないというわけだ。 知っていますか?汗でわかる病気のサイン! ●以前より汗臭い…糖尿病、甲状腺の病気 ●アンモニア臭がある…肝臓や腎臓病 ●汗の量が多くなる、寝汗をかく…糖尿病、心臓病 ●体の左、または右側ばかり汗をかく…脳梗塞の前ぶれ症状 不快な汗「盗汗(とうかん)」とは 寝ているときにかく汗はさらさらしておらず、ニオイのある不快なものが多い。これを「盗汗」といい、漢方では心身の不調の表れとしている。精神的な緊張状態や疲労、不摂生による胃腸障害、生理不順、更年期障害などで起こりやすい。 公開日:2006年7月31日
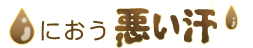
「爽快な汗を思い切り流してみたい!」そんな人が増えているのか、最近、健康志向派の注目を集めているのが「岩盤浴」。岩盤浴とは、温かい石の上に寝転がるサウナのようなもの。体を内側から温め、老廃物を排出して新陳代謝を活発にする。さまざまな健康効果が期待できるとされるが、その秘密は「発汗作用」にある。そこで今回は、「汗」が持つさまざまな役割について迫ってみよう! 目次 汗かき下手が増えている? におう悪い汗 におわない良い汗 汗かき下手が増えている? 温暖化の影響か、暑い日がぐっと増えた近頃の夏。ところがその一方で、汗をかきやすい人は減りつつあるといわれている。理由は、私たちの体が温度変化についていけなくなっていること。最近は夏は冷房、冬は暖房によって室温調節した環境で過ごす人が多い。汗には、体外に熱を放出し、体温を一定に保つはたらきがあるが、年間を通してその必要がなくなっているため、体の温度調節機能そのものがはたらかなくなっているのだ。 もともと日本人はよく汗をかく民族だった。というのも、汗の量は「能動汗腺」という汗腺の数によって決まるからだ。人間の汗腺数は同じだが、この能動汗腺数は民族によって差がある。例えば、ロシア人は少ないが、インドネシア人では多い。高温多湿の環境に暮らす日本人もまた、たくさんの能動汗腺を持っているというわけだ。 それにもかかわらず、最近、私たちの汗の量が減っているのは、生活環境が変化しているから。能動汗腺数は生後3年までに決まるとされるが、汗をかかない生活をしていると、数は増えず、汗をかきにくくなってしまう。さらに長年、汗をかかずにいると、能動汗腺の機能低下が起こるのだ。 汗の量が減ると、体温調節機能が壊れるばかりではない。ホルモンバランスが崩れ、免疫力も低下してしまう。自立神経失調症に発展し、「起立性調節障害」に発展することも。起立性調節障害とは、血管の機能不全から、めまいや立ちくらみなどが起こる病気のこと。 また、能動汗腺の機能低下が起こっている場合、たまに汗をかくと、水分とともにミネラル分まで一緒に排出されてしまう。健康な汗腺はミネラル分を再吸収して血液中に戻すことができるが、弱った汗腺にはそれができない。その結果、ミネラル分を含みベタベタした汗をかくことになるのだ。しかも、ミネラル分が失われることにより、体の生理機能が狂い、体を重く感じる、疲れが残るなどの体調不良が起こりやすくなる。 日ごろしっかり汗をかいている人は、汗腺が水分のみを排出し、さらさらとした汗を流すことができる。ニオイやベタつきも少なく、不快感を伴わないのが特徴だ。上手に汗をかけば、このほかさまざまな健康効果が期待できるだろう。 ●疲労物質を押し流す! 筋肉が疲労するとできる乳酸や二酸化炭素。汗はこれらを体外へ押し流し、疲労回復に一役買っている。 ●自律神経がバランスを保つ 汗をかかない生活を長く続けると、自律神経が正常に機能しなくなってしまう。ストレスがたまり、心身に悪影響を与えることも。 ●汗をかいてカロリー消費 汗は蒸発する時に体から気化熱を奪い、カロリーを消費してくれる。したがって肥満の解消にもGood! ●肌の保護 汗の水分と一緒に分泌される皮脂が、肌の乾燥を防ぎ、肌の潤いを守る。新陳代謝も促されるため、汗は美肌づくりにも欠かせない。 エアコンに頼って体を甘やかしてばかりいると、「良い汗」はかけない。冷え切ったオフィスで仕事に追われ、冷や汗をかいているあなた!冷房の温度設定はほどほどにして、健康的な汗を流すよう心がけてはどうだろうか。 公開日:2005年7月19日

必要以上に汗をかいてしまう病気を「多汗症」という。日常生活に支障がでることもあるほど、汗をかいてしまう病気だ。多汗症とはどんな病気なのか、またその治療法を紹介する。 目次 多汗症ってどんな病気? 多汗症の原因は? 多汗症の裏に病気が隠れていることもある 多汗症を治療するには? 多汗症ってどんな病気? 多汗症とは、読んで字のごとく「必要以上にたくさんの汗をかく病気」のこと。特に、緊張したときやびっくりしたときにかく精神性発汗(エクリン腺からの分泌)による汗の異常である。なかでも手のひらや足の裏に限定して大量に汗をかく場合には、「手掌足蹠多汗症(しゅしょうそくせきたかんしょう)」という。 精神性発汗の特徴は、手のひらや足の裏に大量に汗をかくこと。わきの下や顔面を伴うこともあるが、体からはあまり汗が出ない。 多汗症に気づくきっかけは、字を書こうと思ったら紙が濡れて破れてしまった、フォークダンスのとき、他の人と手をつなごうと思ったら自分の手がべたべたしていたなど。汗をかく量も「いつも手足が湿っている」程度の人から「滴り落ちるほどいつも濡れている」人までさまざま。 「ピアノを弾こうとしたら、鍵盤から指が滑ってしまう」とか、「好きな人と手をつなぐチャンスだったのに、手の汗が気になってダメになってしまった」「パソコンが汗で壊れてしまった」など、生活に支障を感じる場合も少なくないようだ。 もちろん、ある程度の汗はかいて当然。誰にでもあることなので必要以上に「私って多汗症?」などと思わないようにしよう。 多汗症の原因は? 以前は、人よりも緊張しやすいからとか、神経質だと汗をかくのだと考えられ、「気の持ちようで汗はかかない」と思われていた。しかし、実際多汗症の人は自宅でリラックスしていても手のひらから汗が出たり、朝目覚めたとたんに汗をかきはじめることもある。 多汗症の場合は、精神的に緊張したから汗がたくさん出るのではなく、緊張したときに発汗を促す「交感神経」が敏感すぎるために汗を多くかいてしまうようだ。そのため、朝目覚めたなど、ごく普通に交感神経が活動しはじめただけで、人一倍汗をかいてしまう。 多汗症は必ずしも精神的な要因による病気とは言えないのだ。 多汗症の裏に病気が隠れていることもある 汗が大量に出る原因として、何らかの病気が関係している場合もある。 汗が必要以上に出る主な病気 更年期障害の症状のひとつ 更年期障害の症状のひとつに、かっと汗をかいたと思ったらすぐにひいてしまうことがある。これは、更年期になって卵巣機能が衰えてくると発汗を抑制するエストロゲンというホルモンの分泌が低下するため。 甲状腺機能亢進症によるもの 甲状腺機能亢進症になると、甲状腺ホルモンが増加して基礎代謝が高まり、全身性の多汗が見られる。 褐色細胞腫によるもの 副腎腫瘍の一種である褐色細胞腫になると、アドレナリンというホルモンが大量に分泌され、この代謝を高めるために多汗になることもある。 多汗症を治療するには? 多汗症を治療したい場合、何科を受診すればよいのだろうか。 実際、多汗症の人は、手の皮膚からの汗だからと皮膚科へ行くケースが多いようだ。また、多汗を精神的なものと考えて、精神科や心療内科へ行ったり、ワキガなどの治療も行っている美容外科へ行くことも。多汗症の治療法はいくつかあるので自分にいちばん合った方法をじっくり選ぼう。そのために複数の科を受診するのもよいだろう。とにかく自分で納得できる方法を見つけることが大切だ。 多汗症の治療方法 ●心身療法 多汗症は必ずしも精神的なものが要因ではないが、場合によっては心身療法によって症状が軽減することがある。 汗に対して恐怖感や強い不安感を持っているなら、この方法を試してみるとよいだろう。なかには多汗が原因で、「人前に出られない」「人の視線が気になって仕方がない」などの心の病にかかってしまうケースもあるからだ。 心身療法では主にカウンセリングによって汗に対するマイナス意識を変えていったり、自律訓練法によって自律神経(交感神経や副交感神経)のはたらきを整えるなどの療法を行っている。 ●薬物療法 多汗症の場合、汗に対する不安を取り除くために、精神安定剤(抗不安剤)を処方されることがある。ただし、この薬は直接汗をとめる作用があるわけではなく、緊張を緩和することが目的だ。また、東洋医学でも多汗症に対する治療があるようだ。ただし、体の体質に対しての治療なので、利用する際は東洋医学専門医か専門薬剤師と相談しよう。 直接、汗に作用する薬としては、汗をかくときに交感神経の末端から出ているアセチルコリンという化学物質を止める薬(抗コリン剤)がある。しかし、この神経遮断薬は、腺からの分泌を止めるための薬で、手のひらだけではなく全身に作用し、また口渇、便秘、胃腸障害などの副作用があると言われている。使用を考えるなら、必ず、医師と相談の上、慎重な判断を。 ●制汗剤の使用 とにかく、一時的なものでもよいので、手のひら、足の裏の汗を止めたいというときは、制汗剤を使用するという手もある。現在、制汗剤は市販されている種類も多く、どのタイプを使用するかは自分の状況に合わせて選ぶとよいだろう。 また、アルミニウム塩などを用いた制汗剤は効果的だと言われている。ただし、これは物理的に汗が出てくるのを止めるだけのものであり、多汗症そのものを治療するものではない。また、アルミニウムは人体への有害性も指摘されているので、使用する場合には、注意事項をよく読み、用法をきちんと守るようにしよう。 ●手術による治療 多汗症の治療には手術もある。 発汗を作用している交感神経をブロックするというもの。手のひらの汗を止める場合、「胸腔鏡下交換神経切除術」と言われる胸腔鏡(スコープ)を使って胸部交感神経を遮断する手術を用いる。全身麻酔をし、わきの下の皮膚を2~4ミリほど切って行われる。傷口も小さく、手術時間も短いため、患者への負担は少ない。 同様に、足の裏の汗を止めるには、腰椎の交感神経をブロックする手術がある。 ただし、どちらの手術も手のひらや足の裏の汗はストップされるものの、術後、手のひらや足の裏以外の部分から汗が出る代謝性発汗(反射性発汗)が起こることがある。 しかし、手術の前に代謝性発汗を予測することは難しく、かなり個人差があることなので、手術をする場合には、医師とよく相談し、心配なことは事前に確認しておくこと。 ●ちょっとした工夫でも汗&ニオイは減らせる 「手術をする程でもないし、治療も大変そう…」という人には、一時的な対処法ではあるが、汗を減らす方法やニオイをとる入浴法がおすすめ。さっそく試してみよう! 汗っかきの人のための知って得する情報 公開日:2003年6月9日

べたべたしたり、ニオイがしたり、汗は何かと嫌われがちな存在。しかし、実際には体温調節機能など、人間にとって汗は大切なもの。人がどうして汗をかくのか、その理由と仕組みを紹介する。 目次 汗の大切な役割は体温調節 体温調節のためにはたらく「エクリン腺」 ニオイのもととなる汗を出す「アポクリン腺」 汗の大切な役割は体温調節 暑いときや緊張したとき、顔や手のひら、体からじわっと出てくる汗。べたべたするし、服は濡れるし、化粧は崩れるし、なんだかニオイそうだし…と、ちょっと嫌われがち。しかし、そうは言っても人間にとって汗は必要なものなのだ。もし、人が汗をかかなかったらどうなるのだろうか。 汗の重要な役割は、「体温調節」。人は一定の体温を保った恒温動物である。心臓などの臓器の温度は核心温と呼ばれ、およそ37度に保たれていると言われている。これに対し、皮ふ表面や筋肉などの温度は外殻温と呼ばれ、体の内外の熱を入れかえる役割を果たしている。 運動や暑い外気に触れるなど、体内で熱が生産されたときに、体外へ熱を放出することで熱量のバランスを取り、体温を一定に保っているのである。その一役を担っているのが汗だ。汗には熱を体外へ放出するという大切な役割があるのだ。 体温調節のためにはたらく「エクリン腺」 汗が出る腺は2種類ある。 「エクリン腺」は、爪の下や唇以外の、体のほとんどの部分に分布している。皮膚の表面から1~3ミリの所、真皮層から皮下組織の上部にかけて存在する。その大きさはかなり小さく肉眼ではほとんどみえない。多い人は約500万個、少ない人で約200万個、平均すると約350万個ある。しかし、すべてのエクリン腺が汗を出すわけではなく、実際に活動しているのは半分程度。この活動しているエクリン腺の量が、汗の量を左右し、体温調節のためにはたらいているのだ。 エクリン腺からの汗はほとんど(99%以上)が水で、そのほかにはごく少量のナトリウムや塩素、カリウム、カルシウム、重炭酸イオン、尿素、アンモニアなどが含まれている。この成分は、血漿の成分とほぼ同じ。 エクリン腺からの発汗の種類 ●温熱性発汗 暑いときや運動したときなど、体温調節のために体からかく汗。 ●精神性発汗 緊張したときや何かに驚いたときに出る冷や汗。手のひらや足の裏、わきの下などから出る。 ●味覚性発汗 辛い物を食べたときに額や鼻などにかく汗。 ニオイのもととなる汗を出す「アポクリン腺」 アポクリン腺の分布 外耳道や外陰部などごく限られた場所にのみ分布し、ほとんどがわきの下にある。皮下組織の上部で毛穴と一致した所に存在し、その腺体はわきの下では肉眼で十分見えるほど大きい。 アポクリン腺の役割は、体温調節ではなくニオイの原因となる汗を出すこと。動物にとっては仲間同士の確認や異性をひきつけるフェロモンのような役割があるため、体臭は必要なもの。人間のニオイにも同じような役割があるとも言われている。しかし、最近は、ニオイに敏感な人が多く、アポクリン腺の分泌液のニオイは「ワキガ」などと呼ばれて、すっかり嫌われている。 アポクリン腺の量は人種によって、また個人によってもかなり差がある。また、一般的には黒人・欧米人には多く、日本人や中国人には少ないと言われている。 アポクリン腺からの汗の成分は、塩分が少なくたんぱく質・脂質・糖質・アンモニア・ピルビン酸・鉄分などさまざまな成分が含まれており、粘り気がある。 「わきの下の汗」=「ニオイ」の原因なの? わきの下にかく汗は不快だし、ニオイも気になるもの。「もしかしてワキガかしら?」と悩んでいる人も多いようだ。しかし、わきの下の汗がにおうのとワキガ体質は別のもの。 いわゆる「ワキガ体質」の人は、そうではない人に比べてニオイのもととなる汗を出す「アポクリン腺」 の数が多いと言われている。もし、「このニオイはワキガかな?」と悩んでいるなら、一度、自己チェックをしてみよう! ワキガ体質自己チェック:ワキの下のニオイを防ぐ 公開日:2003年6月9日

体臭は個性、あなたの魅力!とはいえ、この暑さです。体臭が強くなっては自分でもうっとうしいもの。「汗クサイ」なんて言われないためにも、ちょっと生活や食事にひと工夫していきましょう。 目次 体臭対策は清潔第一。食べ物にも注意! 体臭を抑えるために避けたい食品 意識して摂りたい抗酸化食品 部位別ニオイの原因とケア法 体臭対策は清潔第一。食べ物にも注意! 体臭対策でまず最初に押さえたいのが気持ち的なポイント。「汗をかきたくない」「汗をかくとクサイ→人に嫌われる」といった頭の中の思考回路を一度断ち切るのだ。何故かといえば、気にすれば気にするほど汗をかくからだ。これを「精神性発汗」という。例えば緊張すると冷や汗が出たり、手に汗が浮いたりする。これが精神性発汗だ。汗をかくことは自然なこと。汗へのケアをすれば良いのだから、それ以上の心配は抑えていこう。 次にケア。これは清潔第一。毎日お風呂に入る、下着をマメに取り替える…といったことは基本だが、近ごろはさまざまな制汗剤が出回っているので、出かける前に使用しておくと良い。ちなみに、制汗剤とデオドラント剤はもともとの発想が違うのはご存知だろうか。制汗剤は汗腺にはたらきかけて汗を出にくくするもの、デオドラント剤は臭いをつくり出す雑菌を退治したり繁殖を阻止するもの。覚えておきたい。 汗をかいたらコマメに対処を。汗を拭き取り、サッパリしよう。これにもシート状の拭き取り剤が多数市販されているので便利だ。汗をかけば誰でも気持ちが悪い。肌だって同じなのだ。汗をかいたまま放置されれば臭いを発生させる。つまり汗臭さや体臭が強くなるのは「不快だ!」という肌からのサインともいえる。 そして、もうひとつ気をつけたいのが食生活。表のように、基本的に肉類の多い食生活をしていると体臭は強くなると言われている。欧米人が体臭が強いのも、食生活にあるとされる。逆に多く摂りたいのが、抗酸化食品。先にも話した通り、体臭の原因は脂質などの酸化。酸化を防げば体臭も抑えることができるのである。 体臭を抑えるために避けたい食品 ●動物性たんぱく質 動物性たんぱく質や脂肪を多く含む肉や乳製品を多く摂ると、脂質の分泌が増え、臭いのモトとなる。汗もかきやすくなる。肉・牛乳・チーズなどは控えめにしよう。 ●辛いもの、臭いの強いもの 辛いものを食べると汗が出るのは誰もが経験したことがあるはず。またニンニク・ニラ・ネギ・ラッキョウなどが臭いの原因であることも周知の事実。夏は食べる時間や場所を選びたい。 意識して摂りたい抗酸化食品 ●ビタミンE 小麦胚芽、植物油、アーモンド、ピーナッツ、うなぎ、緑黄色野菜など ●ビタミンB2 どじょう、うなぎ、レバー、さば、干ししいたけ、強化米、納豆など 部位別ニオイの原因とケア法 特に気になる部位には、適材適所の臭い対策をしよう。 部位 ニオイの原因 対策 頭 頭皮や髪に皮脂がたまると細菌に分解されて臭いが発生。たばこなどの臭いが移りやすいことも悪臭の原因に。 コマメに洗う。また、濡れていると臭いが移りやすいので、よく乾かす。 口 唾液の分泌が少なくなると細菌が繁殖し、食べカスの分解や発酵がすすむために悪臭が発生。 よく噛んで食べ、唾液の分泌を促す。食べたら歯磨きをし、臭いの原因となる食べカスを残さない。口の中が渇いたら適度な水分を、ない場合はガムなどでも。 脇の下 アポクリン腺による独特の臭いが発生。 吸汗性の高い下着をつける。消臭剤を利用する。食生活に注意する。 生殖器 アポクリン腺と、恥垢によって臭いが発生。 コマメに洗う。ただし、石けんなどの洗い残しがあると、それ自体が臭いのモトに。シャワーなどで洗い流す程度が良い。 足 足の裏に密集したエクリン腺からの汗を雑菌が分解。脂質とも混ざり合い、悪臭が発生。 ほど良いゆとりがあり、通気性の高い靴を選ぶ。2日続けて同じ靴を履かない。ときどき靴内をアルコールで拭くなどして靴内の雑菌を排除する。 公開日:2002年7月29日
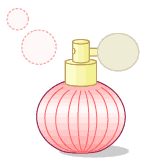
広辞苑によると体臭とは「皮膚の汗腺・皮脂腺の分泌物から生ずる一種の臭気」、国語辞典に至っては「からだのにおい」と素っ気ないです。でも、汗をかくこの季節、体臭を気にしないでいられる人は少ないのではないでしょうか。特に潔癖症、臭い過敏症ともいえる現代では、気になるのが体臭です。 目次 汗と体臭と、個性と 体臭の発生源とその理由 実は「ニオイ」に恋してる!? ただし、こんな臭いにはご用心 汗と体臭と、個性と 体臭ができるメカニズムは、ほぼ解明されている。主なものは下表の通りで、つまり脂質の酸化が大きな原因といえる。でも、だが、しかし。体臭は人によって臭いの種類も違えば、臭う強さも違う。同じ脂質が酸化するなら、その中身が違うのは変だ!と感じる人もいるのではないだろうか。実は、この辺のことはまだ解明されきれていない。ただ、体臭が「HLA」という遺伝子に関係しており、個人差があることはわかっている。 ニンゲンが動物である以上、ほかの動物と同様にその個体を識別するもの、と捉えるのが妥当な線といえるのだろう。そう考えれば一般的に体臭が薄いといわれる日本人でも、人によって臭いがほとんどなかったり、あるいは体臭そのものが良い香りだという幸運な人がいる一方、臭いが強かったり、あるいは自分の体臭は悪臭だと思い込んで悩む人がいるのもうなずける。 ある識者の間では、「自分の体臭は悪臭で、人に嫌われるのではないか」といった不安や悩みを持つことこそが、現代の深刻な心の病のひとつだと言われているほど。当然だが、「ワキガ」も病気ではないのである。まずは自分の個性のひとつとして、体臭を前向きに捉えることから対処してみたい。 体臭の発生源とその理由 発生源 はたらき 体臭となる理由 皮脂腺 皮脂を分泌し、体の表面を守り、潤いを与える。 空気に触れることで酸化し、臭いが生じる。 汗腺(エクリン腺) 汗を出すことで体温と水分を調整している。 汗そのものはほとんど臭いがない。ただ、上記の皮脂と混ざり合い、雑菌が繁殖するなどして臭いを発生させる。 汗腺(アポクリン腺) 異性へのアピール!? 脇の下、乳輪、外陰部など限られた部分にのみあり、この腺から分泌される汗には脂肪、鉄分、尿素、アンモニアなどが含まれ、汗そのものが大なり小なり臭いがある。 実は「ニオイ」に恋してる!? 面白い研究結果がある。未婚の女性に、男性の着たTシャツの臭いをかいでもらい、好き嫌いの関係を探ったところ、父親由来の臭いの遺伝子(HLA)を多く持つ男性に好意を持つ傾向があることがわかったというのだ。 これを推測していくと、女性は父親の、男性は母親の臭いと似ている異性を好むという仮説も成り立つ。また、特に脇の下の臭いは、思春期以降に出てくるため、フェロモンと関係しているといった説も根強くある。とかく否定されがちな存在だが、体臭はもしかしたら異性に好き嫌いを判定させる好材料なのかもしれない。 ちなみに、日本ではあまり発達してこなかったものに「香水」がある。体臭が日本人より強い欧米人は、体臭を隠すために香水を使う文化を発達させてきた、といった説がまことしやかに語られてきたが、これはまったくの俗説。体臭を気にしはじめた歴史より、香料を愛用しはじめた歴史のほうが圧倒的に古いのである。また、この香水を選ぶ際、最初はつい「香りが好き」といった基準で選びがちだが、香水は自分の体臭や体温と相まって香りを醸し出すもの。最初から体臭ありき、で発想し、選ぶのが正解なのだ。 かの女優、マリリン・モンローはシャネルNo.5をネグリジェにしていた、という話はあまりにも有名だが、これなどもモンローの体臭と組み合わされたとき、とても魅惑的な香りを放っただろうと考えられる。自分の体臭と体温。それらとの組み合わせで選ぶ香水。そんな視点で香水を楽しめば、体臭そのものが自分の魅力をいっそう引き出す要素となるのだ。 ただし、こんな臭いにはご用心 体から発せられる臭いには個人差があり、臭いの強さもまた人それぞれ。では、あるが、ときに臭いの原因が病気にあることも。例えば、糖尿病になると甘い臭いがするようになり、甲状腺機能亢進症やパーキンソン氏病になると、皮脂腺が刺激され、独特の体臭がでるようになると言われる。また、口臭がひどい場合は内臓疾患の可能性も。こうしたことをしっかりセルフチェックするためにも、日頃の自分の体臭を知っておくことは大切なのだ。体臭がいつもと違う、変わってきた、ケアをいろいろしても臭いが軽減されない…こんなときは、一度専門医に相談してみよう。 公開日:2002年7月29日
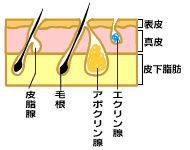
体のニオイと密接な関係がある汗。あなたは汗のことをどれくらい知っていますか? Q1 汗の役割のひとつは体温調節機能である。 ホント ウソ Q2 皮膚にある汗腺にはエクリン腺とアポクリン腺があるが、ワキガの原因にもなるわきに多い汗腺はエクリン腺である。 ホント ウソ Q3 水を飲む量が多くなればなるほど、汗の量も増える。 ホント ウソ Q4 暑い時に出る汗とヒヤッとした時に出る汗は同じである。 ホント ウソ Q5 肉をたくさん食べる人は汗をかきやすい。 ホント ウソ Q6 耳垢が湿っている人はワキガの人が多い。 ホント ウソ Q1 汗の役割のひとつは体温調節機能である。 汗には体温を調節する大切な役割があります。例えば、風邪をひいて体温が高くなったとき、気温が高くなったとき、運動をして体が熱くなったときなど、汗を出すことで体温を下げ、平熱の36.5度前後に保とうとします。もし、暑いときでも汗が出なかったら、体温がどんどん上がってしまい、熱中症になってしまい、命を落としかねません。 ですが、最近はエアコンなどの空調設備が整ったおかげで、夏でも汗をかくことが少なくなり、汗をかいて体温調節する機能が失われつつあります。その結果、低体温児(平熱が低い)が増えたり、自律神経系が弱ってしまう傾向が見られます。 というわけで、正解は「ホント」 Q2 皮膚にある汗腺にはエクリン腺とアポクリン腺があるが、ワキガの原因にもなるわきに多い汗腺はエクリン腺である。 汗腺にはエクリン腺と呼ばれる小汗腺とアポクリン腺と呼ばれる大汗腺があります。エクリン腺は真皮層という皮膚の表面に近い所に分布し、ほぼ全身にあるが、とくに手のひらや足の裏に多く、また熱に弱い脳を守るために、頭にも多く分布しています。 一方、アポクリン腺は、皮膚の深い所(皮下組織)にあり、わきの下や陰部、乳輪、耳の孔(外耳道)など特定の場所にのみ存在します。乳白色の粘り気のある液体を分泌し、これがニオイの原因となります。 ワキガはアポクリン腺から分泌された汗に、その汗が原因で皮膚表面に存在する細菌(ジフテロイド菌など)が繁殖して起こります。さらに、エクリン腺から出る汗によってニオイが周囲に撒き散らされてしまいます。 というわけで、正解は「ウソ」 Q3 水を飲む量が多くなればなるほど、汗の量も増える。 一般的には、健康な状態で水をたくさん飲むと尿として排泄されるため、生理的な汗が増えるわけではありません。 人の口から入った水は血液に吸収されて腎臓でろ過されます。このとき、必要でない老廃物が水とともに尿となって排出されます。よって、水を大量に飲むと尿は増えますが、汗の量はそれほど変わらないのです。 また、ミネラルや塩分を多く含むスポーツ飲料などを飲むと、血液中の塩分濃度が高くなってかえって汗が減ることもあります。 というわけで、正解は「ウソ」 Q4 暑い時に出る汗とヒヤッとした時に出る汗は同じである。 汗には、暑いときや運動したときなどに体温調節のために出る温熱性発汗、緊張したり驚いたときに出る精神性発汗、辛いものなどを食べたときに出る味覚性発汗などがあります。 このうち、緊張したり恥ずかしい思いや怖い経験などをしたときに出るいわゆる「冷や汗」は、体温調節とは関係なく、手のひらや足の裏にどっと出て引いていきます。 これに対し、温熱性発汗は体温調節のために手のひらや足の裏以外の体の表面からじわじわと持続して出ます。つまり、2つの発汗は種類も出方も出る部位もまったく異なるものです。 というわけで、正解は「ホント」 Q5 肉をたくさん食べる人は汗をかきやすい。 口から入った食物は、消化管で消化吸収され、肝臓でエネルギーに変えられます。その際、熱が発生しますが、たんぱく質の場合、糖質などに比べて約5倍も多くの熱を生産します。つまり、たんぱく質の多い肉類をたくさん食べると体温が上がり、そのため汗も出やすくなります。 また、脂肪は皮下組織に蓄積され、アポクリン腺や皮脂腺を刺激してワキガ臭を強くします。 「汗を減らしたい」「ニオイが気になる」という人は肉よりは魚や野菜(とくに緑黄色野菜)など、高栄養・低カロリーの食品がおすすめです。 というわけで、正解は「ホント」 Q6 耳垢が湿っている人はワキガの人が多い。 耳垢がかさかさしていて耳かきで取れる人と湿っていて綿棒で掃除する人がいます。一概には言えないが、ワキガ体質の人は湿った耳垢の人が多いようです。 また、一般にワキガ体質は遺伝すると言われています。優勢遺伝のため、親がワキガ体質なら子どもには3割程度遺伝すると言われています。 というわけで、正解は「ホント」

暑い日は、汗をよくかきます。すると、気になるのが体のニオイです。とくにワキの下のニオイなどは気になってしまいます。ニオイをおさえる方法をご紹介します。 目次 清潔志向が生んだ無臭の世の中 これでニオイをシャットアウト! それでも気になる人はワキガ手術もある 清潔志向が生んだ無臭の世の中 欧米人の体臭はきついと言われますが、これは肉食中心の食生活によるところが大きいようです。それに対して、日本人は比較的体臭の少ない民族です。 しかし最近では、日本人は、必要以上にニオイに敏感になっていると言われています。昔はとくに女性がニオイを嫌悪する傾向がありましたが、最近は男性でもかなり自分のニオイを気にする人が増えてきました。外出先であたりを見まわしてみても、鼻につくニオイはほとんどなく、また家庭でも消臭商品が売れているのは、清潔好きな日本人のニオイに対する嫌悪からでしょう。 これでニオイをシャットアウト! 体のニオイはこうすればおさえられます。 清潔にすること 当たり前ですが、こまめに清潔にしていれば、ニオイはかなりおさえられます。つまり、ニオイの原因となる細菌を洗い落とせばニオイは消えるのです。 まず、温水シャワーを浴びた後に冷水シャワーを浴びると毛穴がきゅっと引き締まって汗の分泌がおさえられます。足もとのニオイが気になる人は、足もとだけでも実行すると靴むれなどの嫌なニオイをシャットアウトできます。 高脂肪の食べ物をひかえる 肉や牛乳、チーズといった動物性脂肪の食事をとると、体内でエネルギーに変わり、体温を上昇させます。すると、汗が出やすくなり、ニオイの原因となる皮脂分泌を過剰にする傾向があります。 また、日常生活でストレスをためることが緊張状態になり、通常より汗が出やすくなります。ストレスをためない生活を心がけましょう。 制汗剤・消臭剤など市販の商品を上手に使う 制汗剤には、スプレーのほか、スティックタイプ、ロールオンタイプもあります。殺菌力の高いワキガ治療クリームや、ジェルタイプのものまでいろいろです。必ず皮膚を清潔にしてから使いましょう。また香り付きのものは体臭と混ざってかえって悪臭になりかねないので、無香性のものがおすすめです。 時と場合によって使い分けるのもよいでしょう。外出前には効果を長時間持続させる直接肌に塗りこむタイプ、外出先では汗を抑える効果のある制汗スプレータイプが携帯しやすくて便利です。また、お風呂上りには全身に使えるジェルやパウダーなどで汗を抑えてさらさらになりましょう。 わき毛の処理をしよう ワキガ体質の人の多くは毛が多く、1つの毛穴から2~3本の毛が生えているような人も少なくありません。乳輪の周りの毛が多かったり、乳輪部にツブツブしたふくらみがあることも多いようです。 ニオイが気になる人はわき毛を処理しましょう。わき毛が伸びたままだと湿っぽくて細菌の巣になりやすいからです。また、アポクリン腺の広がる部分が増え、ニオイが広がるもとになります。 それでも気になる人はワキガ手術もある 手術方法は大きく分けて2つあります。専門機関で相談してみましょう。 ●切開法 皮膚を切ってアポクリン腺を除去します。入院が必要で傷跡も多少残るのですが、効果は高いです。 ●吸引法 脂肪吸引と同じ方法でアポクリン腺を吸引します。傷跡はほとんどなく傷みも少ないです。手術時間は短くその日のうちに帰宅できるが、切開法に比べて効果は低いようです。

お茶に消臭作用があることをご存知でしょうか。口臭対策に、食後にぜひお茶を飲みましょう。また足の臭いの対策にもお茶は役立ちます。 目次 気になる「臭い」は、お茶で消す お酒もたばこもお茶でスッキリ! お茶で民間療法!? 気になる「臭い」は、お茶で消す 最近は「体臭」を気にする人が多いようです。多くは本人の意識過剰とも言われますが、やはりそれでも気になるものではないでしょうか。そんなときにも「お茶」がおすすめです。 ●口臭対策 お茶を飲んでいる食後のお茶は、臭いの元になる食べ物の残りカスを洗い流します。 お茶に含まれる「カテキン」や「フラボノール」の殺菌作用や消臭作用によって臭いを遮断します。 お茶の葉には虫歯を防ぐフッ素も含まれています。 以上のことから、食後にはぜひお茶を飲みましょう。 ●「足の臭い」対策 茶殻の水気をきって、新聞紙などに広げてしっかり天日干ししたものを、不用な古い靴下などに入れて靴の消臭剤として活用します。 お酒もたばこもお茶でスッキリ! お酒に効くお茶パワー! 酔って醜態をさらさないためには、お茶のカフェインが効くようです。カフェインは、酔ってマヒした大脳のはたらきを復活させます。また、カフェインには「利尿作用」もあり、悪酔いの原因となる物質(アセトアルデヒド)を体外に排出してくれます。 二日酔いでツラいときも、熱いお茶でスッキリしましょう。 ●特に効果を期待するなら カフェインは一煎めでほとんど出てしまうので、一煎めを飲みましょう。おすすめは、カフェインを多く含んでいるヤブキタなどの「上級煎茶」です。 たばこに効くお茶パワー! たばこの害のひとつが、体内の「ビタミンC」を破壊してしまうことにあります。1日に必要なビタミンC(50mg)は、たばこを2本吸うだけで破壊されてしまいますが、それをおぎなうのがお茶に含まれるビタミンCです。 ●特に効果を期待するなら カフェイン同様、「上級煎茶」の「第一煎め」がおすすめです。しかしそれでも完全には補いきれないので、やはり禁煙するのが一番です。無理ならば、一服のおともはコーヒーよりも、ぜひお茶を飲みましょう。 その他の効果 ビタミンCは、肌や血管の老化を防ぐほか、抗がん作用もあると言われています。 お茶で民間療法!? お茶の「殺菌作用」を利用した民間療法が、以下の2つです。誰にでも即効があるというものではありませんが、あながち信じられない話でもないようです。 古いお茶の葉があるようなら、どちらも一度試してみてはいかがでしょうか? ●水虫に効く?お茶パワー! お茶で脚を洗っている熱湯で濃く出した茶汁をバケツなどに足がつかるぐらいに入れ、10分ほどその中に足をつけると水虫によく効くそうです。 ●お肌に効く?お茶パワー! お茶の葉を、布袋に20~30gくらい詰めて、入浴剤代わりにお風呂に浮かべるとあせもなどに効果があるという話もあります。

ワキは自分の鼻に近い分ニオイが気になりやすく、自分はワキガではないかと悩む人も多いようですが、実際にワキガ体質の人は日本人の場合10~20人に1人程度のようです。ニオイが気になる人は汗をこまめに拭き取るなど清潔を心がけましょう。 目次 ワキの下のニオイの元凶はアポクリン腺 「汗臭い」と「ワキガ体質」とは違う ワキの下のニオイ対策!7つのポイント ニオイの元凶はアポクリン腺 人間の汗腺にはエクリン腺とアポクリン腺の2種類があります。 前者のエクリン腺はほぼ全身にくまなく分布しており、体温調節を担当しています。ここから出る汗の主成分は、塩分を含んだ水です。 一方、後者のアポクリン腺は、ワキの下をはじめ乳輪、へその周囲、外耳道、外陰部、肛門の周囲など限られた部分にのみ分布し、毛穴に付随した形で開口しています。 このアポクリン腺から出る汗の成分は、脂肪・鉄分・色素・蛍光物質・尿素・アンモニアなど。汗といっても粘り気のある乳白色がかった液体です。 「体臭」に関わってくるのは、このアポクリン腺のほうとなります。分泌される汗自体はほとんど臭いませんが、空気に触れると変質しやすく、皮膚表面の細菌によって分解されると独特のニオイを発するようになります。これが体臭というわけです。エクリン腺からの汗は、このニオイを広がらせる役目を果たします。 ちなみに、いわゆるワキガ体質(腋臭症)の人は、そうでない人に比べて、このアポクリン腺の数が多いようです。 「汗臭い」と「ワキガ体質」とは違う ワキガの人には下に挙げたような共通項が見られるといいます。当てはまるからといって必ずしもワキガ体質とは限りませんが、ひとつの目安にはなるかもしれません。 ワキガ体質自己チェック 耳垢が軟らかい 耳垢には、かさかさして耳かきで掃除できるタイプ(乾性)と湿っていて綿棒で掃除するタイプ(軟性)があります。ワキガ体質の人は後者が多いようです。 下着のワキの部分が黄色っぽくなる 白い下着を繰り返し長く着ると、ワキの部分が黄ばんだり黄緑色になったりします。これはアポクリン腺からの分泌液に含まれる鉄分や色素が原因です(ただし市販の制汗剤によって着色することもあります)。 ワキの下の毛が多い ワキガ体質の人の多くは毛が多く、1つの毛穴から2~3本の毛が生えているような人も少なくありません。乳輪の周りの毛が多かったり、乳輪部にツブツブしたふくらみがあることも多いようです。 遺伝関係がある ワキガ体質は遺伝すると考えられています。親がワキガ体質であれば子供に3割程度遺伝する確率があるといわれます。 ワキの下の汗が多い この場合の汗は、精神的緊張や気温とはあまり関係なく、常時湿っている傾向があります。エクリン腺の汗と違ってやや粘り気が強いことも特徴です。 ニオイ予防 7つのポイント 1. 薬用石けんで朝晩洗う 朝出かける前と夜帰ってから、殺菌効果のある薬用石けんを使って洗うと効果的です。 2. 汗をかいたらこまめに拭く 消臭効果の高い天然フラボノイドをしみこませた汗拭きシートも市販されています。 3. 吸湿性の高い下着を着る かいた汗をすばやく吸ってくれるものを。消臭肌着なるものも売っています。素肌の上にワイシャツやブラウスを直接着るのはやめたほうがよいでしょう。 4. 脂肪を摂りすぎない 脂肪は皮下組織に蓄積され、アポクリン腺や皮脂腺を刺激してワキガ臭を強くします。肉よりは魚や野菜(特に緑黄色野菜)など、高栄養・低カロリー食品がおすすめです。 5. 制汗・消臭剤を使う スプレーのほか、スティックタイプ、ロールオンタイプもあります。殺菌力の高いワキガ治療クリームや、ジェルタイプのものまでいろいろあります。必ず皮膚を清潔にしてから使うこと。また香り付きのものは体臭と混ざってかえって悪臭になりかねないので、無香性のものがおすすめです。 6. 皮膚科で相談し、軟膏薬などを処方してもらう 7. それでも悩みがまったく解消できない時はワキガ手術という手もある 手術方法は大きく分けて2つあります。 切開法…皮膚を切ってアポクリン腺を除去します。入院が必要で傷跡も多少残るが、効果は高いです。 吸引法…脂肪吸引と同じ方法でアポクリン腺を吸引します。傷跡はほとんどなく傷みも少ないようです。手術時間は短くその日のうちに帰宅できるが、切開法に比べて効果は低くなります。
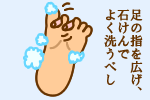
仕事から帰宅して靴を脱いだとたんに嫌なニオイ。宴会で、靴を脱いで座敷に上がるのがちょっと怖い。朝から晩まで靴をはいて仕事に励む会社員にとって、足のニオイは気になるものです。足のニオイを防ぐ方法を紹介します。 目次 ニオイの元となる雑菌を増やさないために 蒸れない靴、ここがポイント! 靴のニオイを防ぐためのちょっとしたケア ニオイの元となる雑菌を増やさないために 足の裏はエクリン腺という汗腺が密集しているため、とにかく汗っかきです。なんと両足で1日にコップ1杯分以上の汗をかくといいます。 この汗自体はほとんどニオイはありませんが、そのままにしておくと、皮膚の表面に住みついている雑菌が、皮脂や汚れ、汗に含まれる有機物を分解し、悪臭が発生します。 しかも靴や靴下で密閉された足は、まさに雑菌が大好きな高温多湿状態です。雑菌の活動はより活発になり、ますますニオイは発生しやすくなります。 靴の蒸れを防ぐ 通気性のいい靴をはく 靴の選び方は「蒸れない靴、ここがポイント!」をご覧ください。 吸湿性の高い靴下をはく ストッキングは綿の靴下などに比べて汗を吸いませんが、吸湿性の高いストッキングを選んだり、つま先ストッキングやインソールをプラスして使ったりするとよいでしょう。 オフィスではサンダルに履きかえる 通勤用の靴は休ませ、湿気を逃しましょう。 同じ靴を毎日はかず、2~3足をまわして使う こまめに足を洗う 手と違って1日に何度も洗ったりしない足は、とかく不潔になりがちです。外から帰ったら足だけでも洗うようにしましょう。タオルで拭いておくだけでもずいぶん違ってきます。 特に汚れがたまりがちな指の間などもしっかり洗うこと。殺菌効果のある薬用石けんがおすすめです。 脂っこい食事を控える 動物性たんぱく質や脂肪を多く含む肉や乳製品を食べると、脂質の分泌が増えてニオイの元をつくり出します。汗もかきやすくなります。 肉・牛乳・チーズなどは控えめにし、野菜や果物などのビタミン類を多く摂るようにしましょう。これは足に限ったことではありません。 足&靴の消臭製品を使いこなす フットスプレー 足用・靴用の消臭スプレーです。靴下やストッキングの上からでもスプレーできます。小さいものを携帯すると便利です。 フットパウダー お風呂あがりに使います。パウダーが汗を吸着します。 足用防臭ジェル 1日1~2回、足の指や裏にマッサージするようにすりこむように使います。 フットシート・五本指ソックス つま先に装着してから靴下をはくと、汗を吸収してくれます。 制汗シート サッと拭くだけでスッキリ爽快です。ストッキングの上からでも使えます。携帯に便利です。 靴用乾燥剤 脱いだ後、靴の中に入れておくだけです。何度も繰り返して使えるタイプもあります。 蒸れない靴、ここがポイント! 蒸れない靴とは、足にぴったりフィットした靴です。というのも、歩くときには足と靴の形にズレが生じ、わずかな隙間ができます。この隙間から、靴の中の蒸れた空気と外の新鮮な空気がすばやく入れ替わるのですが、足に合った靴ほどこの換気がよく行なわれるのです。 ●甲が圧迫されない 甲を締めつけすぎると、血行が妨げられ足は疲労し、汗がよけいに出ます。 ●つま先に適度なゆとりがある 歩くとき足は靴の中で前後にずれるため、つま先には10~15mmの余裕が必要となります。きゅうくつだと換気がうまく行なわれません。 ●カットが浅め カットが深いものは通気性が悪く、靴の中が高温多湿になりやすいようです。 ●かかとのカーブがフィットしている きついとアキレス腱を圧迫して足を傷つけ、ゆるいとスポスポ抜けて歩きにくくなります。歩きにくいと汗をかきやすいので、適度にフィットするものを選びましょう。 ●靴底に弾力がある 弾力がないと、歩いた時に摩擦熱が出て靴の中の温度が上がります。足の動きに合わせて曲がったり元に戻ったりするような弾力性が必要です。 ●通気性のよい素材 吸収した汗をうまく発散させる天然皮革がベストです。最近は人工皮革でも通気性のよいものが出ています。逆にアウトドアシューズのような防水性の高いものは、通気性が悪いことが多いようです。 靴のニオイを防ぐためのちょっとしたケア いくら蒸れない靴を選んでも、毎日履きつづけていたのでは中が乾くヒマもありません。靴の選び方と同様、はいた後のケアにも気を配り、ニオイを防ぎましょう。 ●はいた次の日は「陰干しの日」 靴の水分は一晩では完全に逃げません。1日はいたら次の日は風通しのいい場所で陰干しして、靴の中の湿気を逃がすようにしましょう。間違っても脱いですぐ下駄箱に入れないように。 ●除湿剤で下駄箱や靴の中の湿気をとる 下駄箱や靴の中にたまった湿気は、ニオイの原因になります。除湿剤を入れたり新聞紙を敷いたりして、湿気がたまらないようにしましょう。お菓子の袋に入っている脱臭剤を使ってもよいでしょう。 ●靴の内側を消毒して雑菌をとる アルコール入りのウエットティッシュで靴の内側を拭いて、ニオイのもとになる雑菌をとりましょう。そのあとベビーパウダーをひとふりしてニオイをパウダーに移らせ、最後に固く絞ったタオルで拭き取れば完璧です。

汗を減らす方法、食べ物と汗の関係など、「汗」にまつわる話をまとめました。汗っかきで悩むあなたへ、どれかひとつでも参考になれば幸いです。 目次 肉を食べると汗をかきやすい 辛いものを食べると汗が出る 飲む水の量を減らしても汗は減らない 顔にどっと汗が噴き出したときの対処法 汗のニオイがとれる入浴法いろいろ 肉を食べると汗をかきやすい 口から入った食物は、消化管で消化吸収され、肝臓でエネルギーに変えられます。その際、熱が発生するが、たんぱく質の場合、糖質などに比べて約5倍も多くの熱を産生します。つまり、たんぱく質の多い肉類をたくさん食べると体温が上がり、そのため汗も出やすくなります。汗を減らしたい人は、肉を食べ過ぎないようにしましょう。 辛いものを食べると汗が出る 発汗には、暑いときや運動したときに体温調節のために体全体で汗をかく温熱性発汗、緊張したり驚いたときに汗が出る精神性発汗(冷や汗)のほか、酸味や辛味などの味覚刺激によって額や鼻や唇のところに汗をかく味覚性発汗があります。 辛いものを食べると顔に汗をかくのには、こんなちゃんとした理由があるのです。 飲む水の量を減らしても汗は減らない 通常の健康状態で大量の水を飲んでも、それは汗よりも尿として排泄されることになり、生理的な汗はそれほど増えません。 しかし、水ではなく、ミネラルや塩分を多く含むスポーツ飲料などを多量に飲むと、血液中の塩分濃度が高くなってむしろ汗が減ることがあるといいます。 なお、精神性発汗の場合は水の量をいくら減らそうと汗は減りません。 顔にどっと汗が噴き出したときの対処法 とっさに汗を抑えたいときの、一時的な対処法です。 人前に出たときなどに、顔にどっと汗が噴き出して困った、という経験はありませんか?そんなときは、両手の指で同時に、両側の乳房の上あたりの皮膚を強く痛いほどつねってみましょう。その部分から頭までの発汗が一時的に減少するはずです。 これは「皮膚圧反射」によるもの。人間の体は一部分が圧迫されると、その部分は汗が蒸発しにくくなるため、発汗量が減少します。その際、体全体としての発汗量を一定に保とうという機能がはたらき、その分、ほかの場所で多く汗をかくようになります。これによって、汗をかきたくない場所の汗を抑え、その分、別の場所で発汗するという汗のコントロールが可能になるのです。 汗のニオイがとれる入浴法いろいろ ●緑茶風呂 大きめのお茶バック(薬局などで買える)に、茶葉をカレースプーン2杯分(20~30g)入れ、口をホッチキスで止め、湯船に入れて風呂をたてます。安い緑茶で十分だが、出がらしではなく新しいものを使いましょう。 ●酢風呂 天然醸造酢や黒酢を入れる入浴法です。クエン酸や酢酸のはたらきによって体内の燃焼力を高めると同時に、その酸性によって雑菌の増殖を防いでニオイをおさえます。ユズ風呂もこの一種です。 ●笹風呂 西日本で今でも残る入浴法です。笹の中にたくさん含まれている葉緑素や多糖類などの作用で汗のニオイがとれると考えられています。 ●マコモ風呂 マコモとは川や沼に群生するイネ科の植物です。マコモを加工して、微生物を含んだ粉末にしたものが市販されています。
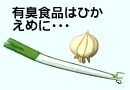
体全体の消臭におすすめの食品・グッズを紹介します。ただしその前に、毎日の生活上の注意で改善できることがないかどうか振りかえってみることも大切です。 目次 ニオイを防ぐ生活 3つの鉄則 ニオイが気になる人におすすめ!消臭食品&グッズ ニオイを防ぐ生活 3つの鉄則 鉄則1:毎日入浴する 体を清潔に保つ、これが基本中の基本です。石けんを使って隅々までよく洗い、1日の汗・汚れはしっかり落としましょう。 鉄則2:有臭食品はひかえめに ニンニク・ニラ・ネギ・ラッキョウなどは有臭食品といわれ、ニオイのことを考えるとできれば避けたいものです。とはいえ栄養的にはすぐれており、健康のためにはぜひとり入れたい食物でもあります。食後に牛乳(消臭効果がある)を飲むなどの対策をしましょう。 鉄則3:汗を吸う衣類を身につける 汗も放置するとニオイの元となります。親水性・通気性のある素材の衣類を選ぶとよいでしょう。素肌に直接ワイシャツを着るなんてもってのほかです。綿の下着を身につけましょう。 ニオイが気になる人におすすめ!消臭食品&グッズ 悪臭の元に作用することで体臭・口臭さらには便臭まで消してくれるという食品や、体に塗ったり拭いたりするだけで消臭するというものなど、世の中にはありがたい商品がたくさん出ています。以下はその一例です。薬局・ドラッグストアなどで探してみましょう。 消臭食品 野菜の粉末食品 ニンジンの葉の粉末、あるいはゴボウ・レンコン・ニンジン・かぼちゃなど何種類もの野菜を粉末にしたものがあります。 豊富な食物繊維が腸内の有害物質を吸着して排泄してくれ、体臭の原因となる脂肪分の酸化も防ぎます。また、含まれているビタミンCにも消臭作用があるといわれています。 カテキン 緑茶に含まれる渋み成分としても有名です。300㎎のカテキンは緑茶3杯分に相当します。がんや高血圧などの予防にもよいといわれます。緑茶を風呂に入れてもよいでしょう。 ミョウバン水 ミョウバンを水に溶かしたものです。スプレーしたり、タオルなどに染み込ませて体を拭いたり、お風呂に入れたりして使います。ミョウバンに含まれるアルミニウムや鉄に殺菌作用があります。 消臭グッズ アルム石 スイス・アルプスのふもとで多く産出される天然石です。水で浸してニオイの気になるところに塗ります。ニオイの元となる雑菌の発育や活動を制御する殺菌作用があります。 消毒エタノール エタノールを薄めたもの(エタノール7:水3ぐらいの割合)をコットンに含ませ、汗をかきやすい部分を拭きます。消臭・殺菌効果があり、清涼感もあります。 消臭肌着 悪臭成分を化学的繊維で消臭します。洗濯しても効果は持続します。
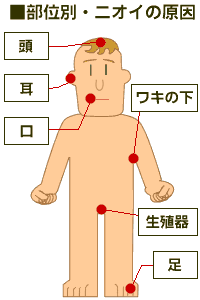
体臭・口臭はただの不快なもの、というわけでもありません。ときには、私たちの体の中の異常を知らせてくれることもあり、そういう意味では必要なものともいえます。 目次 ニオイで健康状態がわかる! 部位別・ニオイの原因 ニオイで健康状態がわかる! 嫌なニオイはできれば消し去ってしまいたいものですが、医師からすれば、体から出るニオイを100%消してしまうのは賛成しがたいようです。なぜなら、ニオイでその人の健康状態がわかることがあるから。 例えば、糖尿病の人の尿からは甘いニオイがしますし、肝性昏睡患者の嘔吐物からはアセトン臭と呼ばれる独特のニオイがします。いくら歯磨きしても口臭がキツイ人は、内臓疾患が疑われることもあります。 漢方医学の世界では、患者から出るニオイで病気を診断する「嗅診」という診断法があるくらいです。 体臭は強い弱いの差こそあれ、だれにでもあるものです。体臭をまったくなくしてしまうのは無理ですし、むしろ不自然なこと。時と場所、状況によって、ニオイをうまくコントロールできるのが一番です。 部位別・ニオイの原因 これは、体の部位ごとに見た、嫌なニオイの主な原因です。 ●頭のニオイ 頭皮や髪に皮脂がたまると細菌に分解されてニオイを放ちます。フケもニオイの原因です。また髪に移ったたばこや焼肉などのニオイが発酵して悪臭の原因になることもあります。 ●耳のニオイ 耳から嫌なにおいがするときは、中耳炎など耳鼻科の病気の疑いがあります。 ●口のニオイ 生理的口臭:朝起きた時や緊張したときなどに生じやすいです(主に唾液の分泌低下が原因)。口の中を清潔に保てばかなり防げます。 病的な口臭:歯槽膿漏・歯肉炎など口の中のトラブルと、胃腸疾患によるものがあります。ほか、肝臓や腎臓の機能低下、糖尿病が原因でも口臭が発生します。 ●ワキの下のニオイ 両腕によって常に閉じられていてニオイがこもりやすい部位です。アポクリン腺から出る汗と皮脂が、皮膚表面の細菌とまじりあってニオイが発生するといわれています。 ●生殖器のニオイ 男性より女性に悩む人が多いようです。カンジダ膣炎、トリコモナス膣炎などの性的感染症やスソワキガなどが原因となっていることもあります。 ●足のニオイ 足から出た汗や皮脂が細菌などの作用で発酵してニオイとなります。手のひらに汗をかきやすい人は足にもかきやすく(精神性発汗)、ニオイが強いことが多くなります。 このうち、特に気にする人が多い「足」「ワキの下」「口」のニオイについて、もう少し詳しい原因と対策を紹介します。 足のニオイを防ぐ ワキの下のニオイを防ぐ 口のニオイを予防する
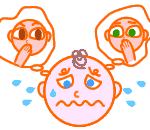
昔の日本人は、体臭をそれほど気にしませんでした。ところがいまは、自分の体臭で悩む人が増えているといいます。それを象徴するのが、デオドラント商品の好調な売れゆきです。日本人はいつの間にニオイを嫌うようになったのでしょうか。 目次 ニオイのない時代 あなたの周りの人も悩んでいるのかも… 気にしすぎるのもひとつの病気 ニオイのない時代 ヨーロッパの人の体臭はきついといわれています。これは伝統的な肉食中心の食生活によるところが大きく、ヨーロッパで香水が発達したのも強い体臭を消すためなのだそう。 それに対して、日本人は比較的体臭の少ない民族です。お香以外に、ニオイへの関心も薄かったようです。それが今ではニオイに敏感な民族になっています。 ニオイを嫌悪する傾向が強まってきたのは、日本の社会から徐々に「生活臭」がなくなってきたことの反映ともいわれます。汲み取り便所の刺激臭は水洗トイレの普及によってなくなり、焼肉店のおいしそうなニオイは無煙ロースターの導入で消え…という具合です。 今の若い世代の人々は、生活臭が街に満ちていた時代を知りません。となれば、生活臭や体臭を嫌悪するのも当然かもしれません。 あなたの周りの人も悩んでいるのかも… 体臭に関する悩みは、その人自身にとってはとても深刻です。ひどい場合は対人恐怖症にまで陥りますし、登校拒否をおこす子供も増えているようです。 例えばあなたに思春期の子供がいる場合、次のような行動が目についたら、それは体臭で悩んでいるというサインかもしれません。 ●入浴時間が急に長くなったり、1日に何度もシャワーを浴びる ●デオドラントグッズを急に買い揃える ●汗をかくのが恐いため、好きだったスポーツや運動を急にやめてしまう 気にしすぎるのもひとつの病気 とはいえ、気にしすぎるのも問題です。実際は臭わないのに体臭がきついと思いこんでしまいます。これがひどくなると、自臭症(自己臭症)という立派な病気になります。実際は違うのに「私が近くにいくとみんな不快そうな顔をする」「私と話をする時にあの人がたばこを吸うのは私の口臭のせいだ」などと思いこんでしまうのです。 だれにでも体臭はあります。自分で臭いと思っても、周りからすれば気がつかないほどのものかもしれません。そして人間は気にしすぎるとよけいに汗をかき、逆効果となってしまいます。 まずは清潔第一。そして気にしすぎないことです。どうしても気になるときは皮膚科で一度相談してみるとよいでしょう。

毎日お風呂に入ってる。 おまけに朝だってシャワーを浴びている。 そんな清潔好きな私の足がクサイなんて…。 「靴さえ脱がなきゃこんな悲惨な目に遭わなかった」なんて思っても、もう後の祭り。 こんなことにならないためにも、夏の足をクールダウン! 汗のせいにしないで! 気温が上昇すれば、汗は自然にかくもの。 特に靴で覆われている足は両足でコップ1杯分の汗をかくこともあるらしい。 でも汗はほとんどが水分と塩分で、残りのほんの少しがタンパク質などの有機成分だとか。 だから汗自体はホントは臭くないのだ。 ところが汗を放置しておくと、皮膚の表面の雑菌と足の汚れや皮脂・汗の有機成分が一緒になって悪さをしでかす。 これがニオイの原因。 もちろんこれは足に限ったことではなく、ヒトの体全体で起こっているのだが、靴の中は湿気も高く、温度も高いので雑菌が生殖しやすい環境なのだ。 これでクサイ足とオサラバだ 第一に 靴から湿気を追放したいもの。 ちょっとカッコ悪いけど、職場ではサンダル履きにするか、靴を脱ぐ時間を作ろう。 短い時間でも効果テキメン。 そして靴を長持ちさせるためにも、1日履いたら次の日は休ませて。 湿気取りの利用や陰干しで徹底的に湿気を追放しよう。 第二に 足を清潔に。 お風呂で体を洗うときには足も丁寧に。 かかとや指の間、爪も洗うこと。 今まであまり丁寧に洗ったことのない人は、意外にたくさんのアカが出るのに驚くはず。 丁寧に洗うと足の裏マッサージにもなるから、就寝前の入浴にぜひオススメ。 第三に 靴選びの時には、特に夏用の靴は通気性のいい素材の物を選んで。 また普通の靴でも、やたらに締め付けずそれでいてフィット感のある大きさなら、靴の中と外の空気の出し入れが可能で、かなりのムレ防止に。 外反母趾などの面からもやたらに窮屈な靴は避けたほうが良い。 やはり履き心地のいい靴が何よりということだ。 そして「今日は帰り道お座敷に上がりそうだ」なんて日は、職場で靴下を取り替えよう。 靴下が吸収した汗を放置しないようにすると、靴の中の湿気もかなり軽減できるはず。 ちなみに日本人は臭い足を「納豆臭い」と表現するが、在日フランス人N嬢の話によれば、フランスではある種のニオイのチーズに対し「ソックスみたいなチーズ」という表現を使うらしい。

汗は小汗腺と大汗腺とに分けられる 汗腺は、皮膚の真皮の深層から皮下組織にかけてあり、小汗腺(エクリン腺)と大汗腺(アポクリン腺)に分けられます。 小汗腺は毛と無関係に存在します。手のひらや足の裏に多く、全身に200~500万個あります。 大汗腺はわきの下や陰部など特定部位にだけ分布し、匂いの強い複雑な成分の汗を出します。このため大汗腺は別名・体臭腺とも呼ばれます。 汗の分泌は1日に700~900ml、運動時には10Lも 汗腺の主なはたらきは、汗を分泌して体の温度を一定に保つことです。汗腺、皮膚、血液は共同して体の空調システムとしてはたらいています。 ただし、手のひら、足の裏、額、わきの下などにある汗腺は、このはたらきとは無関係に感情によって反応します(精神発汗、冷汗)。神経質な人の手のひらがいつも湿っていたり、緊張すると汗をかくのはこのためです。 普通、汗の分泌は1日に700~900ml、夏季や運動時には10Lにものぼります。 なお、乳房は汗腺が特殊化したものです。女性ばかりではなく、これは男性にもあります。





